2018年10月28日(日)に日本女子大学目白キャンパスにて2018年度秋の研究大会を開催しました。当日は、57名の方にご参加いただきました。第一部の自由報告では、7件の発表がありました。続く第二部の企画セッション、Charles Goodwin 先生追悼特別企画「協働としてのインタラクション:言語・身体・参与」は、5名の登壇者からのご発表とディスカッサントによるコメントという盛りだくさんの内容で、フロアとの有意義な議論を通して、今後のEMCA研究について考えることができました。ご報告くださったみなさま,および特別企画にご登壇くださったみなさまより、ご感想をお寄せいただき、こちらに短信としてまとめました。改めて、ご参加いただいたすべての方々に御礼申し上げます.(大会担当世話人:早野薫・岩田夏穂)
内容の詳細は→活動の記録(2018年度)をご覧ください。
| 短信 |
|---|
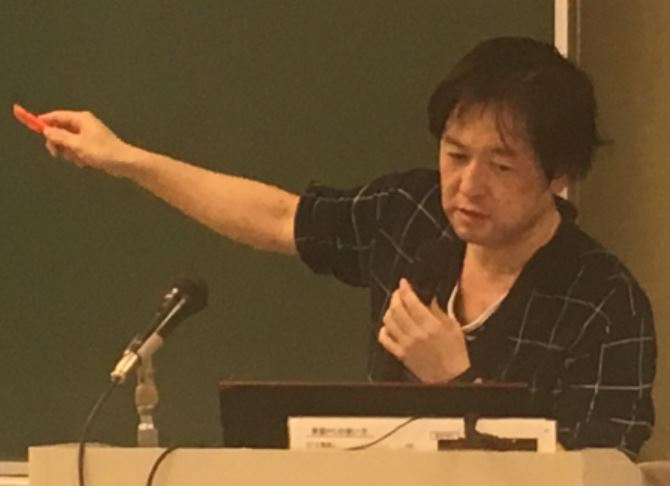 |
 |
 |
 |
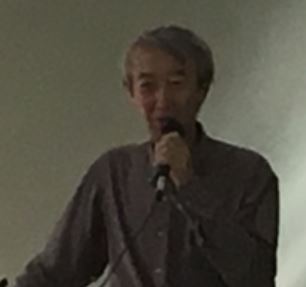 |
 |
 |
第一部 自由報告
第一部会
「日本語学習者会話データコーパスにおける相互行為の対話自動生成への適用に関する一考察」
- 太田博三(放送大学 (社会人学生))
この度は報告の場を頂きまして,感謝申し上げます。もともと分析屋ですので,良い意味でも悪い意味でも,怖いもの知らずに,報告をさせて頂きました.論文作成は,データ分析と同じく,あまりに確立された手法に捕われてもいけませんし,試行錯誤しました.更なる向上に資するつもりです.
一昨年は300-500文字の文章を,コンピューターに文章を作らせる内容を,他で発表致しました.しかし,何か腑に落ちませんでした.深い洞察が抜けていたのでした.私の年齢になりますと,プログラムを走らせ,数理モデルを構築し,出てきた結果を予測や分類などに活かすだけでは,飽き足りません.
実利の場ではコンピューターで終始させ,人間の考察は,極力,少なくさせることが常識です.一方,学術研究の場では,真逆となり,ここで,エスノメソドロジーや会話分析が、私にとって,よきアクセントとなりました.
本報告でのポイントは以下の3つに絞られます.
1つ目は,題名のとおり,条件付き相互行為と位置付け,限りなく離散値でありますが,連続値に近づけたいと考え,ベイズ定理を意識しました.どのテストも,初回より2回目の方が良い結果が期待されます.対人関係も,初対面より複数回の方がスムーズです.次のように簡単化し概念化を試みました.
P(2度目のインタビュー|1度目)
今後は,静的から動的へと実例を用いて,機能拡張を図りたいと考えております.
2つ目は,研究を進めてゆく場合,スクリプトの数やその後,必要に応じて増やす必要のある時に,どういう長短があるかについての考察です.今回,国立国語研究所の「日本語学習者会話データベース」を用いました.これと同じ設計で取得されたKYコーパスを追加し,フィラーや笑いの数を数えますと,不安定な結果になりました.属性の項目で合わせることが解決策と考え,再現性を高められそうと結論づけました.
3つ目は,口頭試験の際に用いられる「突き上げ(Probe)」が,定量分析の項目反応理論に対応していると位置付け,定性的な分析の特徴は,量より質の担保を得られることにあり,経験と深い考察に依存すると考えられます.
これら3つの観点から,工学と人文社会科学との融合の効果が,「自然な」対話システムに生かせるという手ごたえを得ました. 南先生,西澤先生,岡田先生が主力メンバーの月例勉強会に参加し多くを学びました.この場をかりて,感謝の意を表します.
「音楽にかかわる活動におけるエスノメソドロジー——研究文献のレビューとその含意」
- 吉川侑輝氏(慶應義塾大学大学院)
本報告では、音楽にかかわる活動におけるエスノメソドロジー研究の文献レビューを試みました。音楽のエスノメソドロジー研究は、近年、さまざまなフィールドにおいて遂行されています。とはいえこれらの研究は、レッスンやリハーサルをはじめとした練習場面における会話を対象としたものから、本番におけるパフォーマンスや、コンピューターによってデザインされた現代音楽作品を対象としたものまで、実にさまざまです。本報告が目指したのは、研究文献の概観をつうじて研究の広がりを提示すること、そして研究同士が備えている関係を明確にすることでした。検討をつうじて、音楽のエスノメソドロジー研究における対象が、「楽音による時間的秩序の編成」と「発話による連鎖的秩序の編成」とでもいうべき、(少なくとも)2つのタイプを備えていることが主張されました。その上で、音楽にかかわるさまざまな活動の分析をすすめていくことが、エスノメソドロジー研究、音楽についての専門的研究、そして音楽に従事する人びとの日常的活動へと貢献しうる可能性が論じられました。なお当日の読み上げ原稿は、researchmapで公開されていますhttps://researchmap.jp/?action=cv_download_main&upload_id=197050。
質疑応答ではまず、音楽という現象をいかに探求する(べき)かということが議論されました。ひとくちに「音楽」といっても、それを編成していくやり方は、たとえばクラシック音楽のような楽譜があらかじめ存在しているような活動と、ジャズのような半ば即興的に音楽を生みだしていくような活動とでは、大きく異なっています。このとき分析者は、それぞれの活動の特徴にそくして分析を進めていくことに注意しなくてはなりません。質疑応答ではまた、報告者が提示した「楽音による時間的秩序の編成/発話による連鎖的秩序の編成」という区別をめぐって議論がおこなわれました。音楽のエスノメソドロジー研究がこうした区別などのもとで研究をすすめているという報告者による見たての確からしさについては、今後本報告の論文化などを試みるに際して、さらなる検討をすすめていきたいと考えています。
音楽にかかわる活動におけるエスノメソドロジー研究は、近年、明らかに増加しています。しかしながら、その大部分はレッスンやリハーサルなどといった制度的場面における会話分析とでもいうべきものであり、音楽作品や音楽演奏といった対象を分析している研究は、きわめて少数です。この意味で音楽は、エスノメソドロジー研究における、およそ手つかずの領域であるといえるでしょう。本報告が、エスノメソドロジー研究が音楽というフロンティアを開拓していくための一助となることを願ってやみません。
「「法律相談」の(ビデオ・)エスノグラフィー:Garfinkelの試みを引き継ぐワーク研究として」
- 岡田光弘氏(ICU教育研究所・研究員)
フィールド、および研究の経緯など
以下は,2009年以来、ある県の中核となる大学の法学部で実施されている、無料の「法律相談」を観察、録音・録画した。気になった場面を取り上げて、登場者を含む、法の専門家に確認してもらい、核となる事実を確定し、トランスクリプトを作成し、ワーク(方法による達成)研究という視点から分析した。
1972年に、ガーフィンケルとサドナウは、サックスらが、録音素材に基づいて、={会話}=という現象を産出するメカニズムを例証したことをモデルとして、ワーク(方法による達成)についての研究を開始した。当たり前に組織された、ありきたりの活動(Naturally Organized Ordinary Action)には、ハイデガー主義のモノ(ゲシュタルト)という側面とデュルケム派のモノ(社会的な事実)という側面がある。この両面を持つ現象をガーフィンケル(2002)は、={ }=で括って表記している。この視点に基づいた観察から、実際の「法律相談」について、以下の知見を得た。
知見:={質問をする}=
「法律相談」における ={質問をする}=によって、={ペース}=を合わせること、乱すこと、={理解を提示すること}=などが行なわれている(doing)ように見える。一方において、相談者は、まずもって、法的な論点だと聞こえることに耳をそばだて、メモを取る。さらに自分に「有利」な「論点」や「不利」な「論点」については、確認したり、追求したりする質問を行なうことがある。
弁護士による質問には、「いま聞いていること」について尋ねる質問と「それまでに聞いたこと」について尋ねる二つの質問があるようにみえる。開始後、しばらくの間、相談者による事情説明がなされているときには、「いま」「相談者が」「話していること」のなかにある事実、すなわち「いま聞いている」事実を確認するための質問が行なわれる。それに対して,相談者による説明が、一段落した後、「それまでに」「聞いたこと」をもとに、聞きたいことを聞く質問が続いていく。この質問は、「聞いたこと」が、正しく聞けているかどうかについて、={理解を提示する}=ものであり、弁護士の理解について実演することでもある。弁護士による、この二つの質問は、「質問—答え」という隣接対という形式を共有している。だが、置かれている文脈、相談の={ペース}=や、={話題の組織}=とも関わって、「達成されていること」のゲシュタルトが異なっているのである。
「社会学危機論からみたEMCAの現在―「社会学における社会」と「EMCAにおける日常」の同等性,あるいは,活動の同定問題-」
- 樫田美雄(神戸市看護大学)
質的心理学会の質的心理学フォーラム編集委員会(細馬宏通委員長,川島理恵副委員長)のご好意によって「エスノメソドロジー・会話分析の現代的意義と課題」(『質的心理学フォーラム』10号,54~61頁)の抜刷を本体冊子に先行して作成して頂き,このEMCA研で先行配布をすることができた.記して感謝したい.今回の発表は,この「抜刷」に関する解説レジュメを作成し,それを元にして行った.
ところで,元の原稿で工夫したのは,つぎの2点である.
一つ目は以下の通り.従来は,エスノメソドロジーから社会学(構築分析)への「批判」がよく話題とされ,EMCA研内部では,しばしば「批判の妥当さ」を確認する了解可能性の高い発表がなされてきたが,そういう議論の形で言えることはもう飽和しているので,面白くない.そこで,今回は,議論の焦点を切り替えてみた.すなわち,社会学の危機論を前提にすれば,社会学からエスノメソドロジーに救済要請が来ているともいえるのだ,と問題設定を変更し,その救済要請にエスノメソドロジーは応えることができるだろうか,ということを話題にした.
じつは,この「エスノメソドロジーによる社会学の救済可能性の検討」というテーマは,樫田のこの2~3年のテーマであり,直近では,「社会学的に考えることの実践としての『新社会学研究』」(in『新社会学研究』3号,5~13頁,2018年9月)も同じテーマを扱って書かれている.それなりに面白がってもらえたようで満足している.
二つ目は,議論の展開に,話題の本である『社会学の力』(2017年,有斐閣)の中にみてとれる社会学への矛盾した2つの期待の存在を,議論の補助線として活用したことである.その矛盾は,一方では,社会学を「社会への制御可能性を与えるもの」として価値付ける見方があるものの,もう一方では,「社会の制御困難性を認識するもの」として価値付ける見方もある,ということであるが,この矛盾に引き裂かれることから,社会学を救出するアイディアの提供元として,EMCAは働き得るのだ,という議論の進め方をした.こちらもそれなりに面白く思ってもらえたように見えた.
質疑のなかでは,最後に発言して下さった岡田光弘先生のコメントが,印象に残っている.すなわち,「(社会全体を説明する社会学という)強い社会学」像は,もう共有されていないのに,その線で原稿が書かれてしまっている.少し古い議論の仕方をしてしまっているのではないか?,というコメントである.「社会を部分的に説明することもある,という,弱い社会学」像が,現在の若手社会学者やEMCA研究者のリアリティなのだから,そこに依拠すべきだ,というご主張については,なるほど,と得心させられた.
第二部会
「視覚障害者の「知覚」を焦点とする情報授受――歩行訓練場面における触覚と「これ」の組み合わせ使用」
- 南保輔氏(成城大学)西澤弘行氏(常磐大学)、坂井田瑠衣氏(国立情報学研究所)、佐藤貴宣氏(日本学術振興会/京都大学)、秋谷直矩氏(山口大学)、吉村雅樹氏((株)グッドヴィレッジ)
晴眼者のあいだのやりとりにおいては、視覚インプットの共有が自明で前提とされていると思われる。その一方、視覚障害者と晴眼者のあいだのやりとりでは、聴覚や触覚からのインプットが活用されることになる。このときの情報提供と情報の受けとめがどのようになされているのか。これが、本報告の中心的な問いであった。
視覚障害者の歩行訓練場面の記録から、「これ」と障害者の触覚や聴覚インプットが組み合わされて指示が達成されている事例を紹介し検討した。歩いているすぐそばで聞こえたエンジン音を発した車との位置関係、障害者が足裏で感じた点字ブロックがある横断歩道は渡るべきものではないということ、白状があたった電柱の支線カバーの先で道が狭くなっていることなどが、「これ」での指示とともに伝えられていた。
これらの事例を使って議論したかったのは、「情報授受」と「インストラクション」の異同と,「わかる」と「理解する」との対比である。英語の「see」が「わかる」と訳されるように、「わかる」と視覚は緊密に結びついている。晴眼者にとって「道が左に曲がっていること」や「エンジンをかけた車の位置」は見て知ることであり、「理解する」ようなことではない。
また、事例のうちのひとつでは、視覚障害者が独力で何度も歩いている経路について、安全に安心して歩けるように道順を説明するという訓練セッションがあった。「インストラクション」ということばの使用がためらわれる場面であった。その一方で、歩行訓練においてなされているのは,「ことばで世界をつくる」ということだと視覚障害を持つ佐藤はかつて述べたことがある。
残念ながら、報告においてはこれらの論点をうまく展開することはできなかったが、国際学会において英語での報告を予定しているわれわれにとって、今後も追究していく必要のある課題である。
データのなかでは、「これ」のほかに「ここ」も多く使われていた。さらに、「それ」と「これ」の使い分けも今後の課題である。収集したデータは膨大にあり、今後も分析に取り組んでいく。最後になるが、当日コメントをお寄せいただいたみなさんに感謝したい。
「紙面上における表象のアスペクト転換――アスペクト転換の相互行為的達成」
- 鈴木南音氏(千葉大学大学院)
このたびは、発表の機会をいただき、ありがとうございました。貴重なご意見・ご質問を数多く頂いたことを、この場をお借りして、改めて感謝致します。
このたびの報告では、演出家と舞台美術スタッフがやりとりをするなかで、紙面上に描かれた舞台図面がどのようにアスペクト転換がなされるかについて考察いたしました。
演出家が、正面から舞台を見たものとして描いた図案を、スタッフが真上から見下ろした図として眺めてしまった状況において、演出家がスタッフにアスペクト転換を促し、また、アスペクトが転換したことを演出家に向けてスタッフが示すという、そのやり方について、考えました。
そのなかで、演出家が異なる見方を促すために、図を描きながら用いた「こう-」は、平面図との類似性が損なわれるまさしくその瞬間に発話されていました。この発話は、演出家の言いよどみによって遅延されることによって、その瞬間に行なうことが達成されており、このことから、演出家が類似性の欠損に注意を向けさせることに志向しているということを示しました。また、スタッフによる、異なる見方についての気付き・アスペクトのひらめきのタイミングは、演出家がノートを前に押し出し、描き終わることをそれと分かる形で行なった直後に来ていることから、ここでのアスペクト転換のタイミングは、相互行為の秩序のなかで行なわれているということを示しました。そして、ここではアスペクトのひらめきを示すことを通して、スタッフは、平面図を立体図に取って代わるものとして行なった、直前の発話における自身の提案を、自己撤回することを達成したことを、示しました。
これらの現象から、アスペクト転換が個人の内的な過程としてではなく、相互行為の秩序のなかで行なわれ、また、アスペクト転換が示すこと自体、あらたな相互行為を行なうための資源となりうることを明らかにしました。
報告の最後には、ヴィトゲンシュタイン(1958)が行なった類似性とアスペクト転換の議論を参照しながら、ここで起きていた現象と類似性を見出すことについて考察しました。
質疑応答では、多くのご意見とご質問をいただきました。書いている途中で転換させることは、もはや同じものを見ているのではないため、アスペクト転換と言えるのかどうか、などの質問をいただきましたが、あまりうまく答えられず、整理が必要だと感じました。ありがとうございました。
このたびは、駆け出しの私に貴重な発表の場をいただき、また、さまざまなご質問・ご意見・アドバイスを下さり、ありがとうございました。特に、機会を与えてくださった世話人のお二人に、心から感謝致します。いただいたご意見は、今後の研究につなげていきたいと考えております。みなさま、ありがとうございました。
「行為の複合感覚的な達成――視覚化とともに達成されるインストラクション」
- 荒野侑甫氏(千葉大学大学院)
本発表では,実際のギターのレッスンの場面における「視覚化とともに達成されるインストラクション活動」の分析を報告しました.今回報告したインストラクションでは,プロのギタリストであるギター講師がインストラクションに先立って初心者ギタリストの生徒に行なった「フレットに指を近づけて弦を押さえる」という指摘が,具体的にはいかなることなのか,その教示が視覚化と共に行われていました.趣旨としては,講師が生徒に対し,普段ギタリストがどのようにギターの弦を押させているのかという〈感覚〉の教示が,〈複数の知覚資源の複合的な使用〉によって行われているという近年エスノメソドロジー・会話分析のなかで盛り上がりつつある「複合感覚の組織」の議論を展開することでした.
さて,この感覚のインストラクションは,つぎの2つのやり方で行われていました.
(a) 実物のギターで具体的にギターのフレットの押さえる場所を具体的に指で示すこと
(b) ホワイトボードにギターの図を描き,その図を元に説明をすること
これらの視覚化と共に達成されるインストラクションの事例の分析を通じて以下のことが達成されていることを論じました.第一に,相手にとって不確かな命題の把握の仕方を変化させることです.第二に,いかなる構造の要素が行為や活動を構成する意味のあるまとまり(ゲシュタルト)を構成するのかです.前者は,インストラクションの実践的な目的として理解され,さらに後者は,そのことを達成させるためのやり方として理解できます.その具体的なやり方は,まさにさまざまな要素の配置の仕方といってよいでしょう.その配置の仕方は,まさに発話と図示の2つの知覚資源の空間的な配置と言えるかもしれません.そして配置された資源は,共生的に,不確かな命題にかんする相手の把握の仕方を変化させること,このことを達成させていました.
一方で,発表では,事例の分析の方にばかり重点をおいてしまい,ギターの構造やレッスンの参加者たちのことの説明をほとんどできませんでした.それにより,そもそも「フレット」とはギターの構造のなかでいかなるものであるのか,そもそもなんで「フレットに近づけて弾くとよいのか」などをお伝えすることができませんでした.
オーディエンスの皆様からは,発表の質疑応答以外にも,お昼休みや懇親会の席などにおいても,たくさんのコメントをいただきました.ここで,頂いたコメントのすべてに触れることはできませんが,ご指摘いただいた点は,どれも今後のこの研究に有益なものでありました.深謝申し上げます.この発表をもとに実際に論文にする際には,皆様に頂いた意見や疑問点を1つずつ解決し,焦点を絞りながら,また反省点を踏まえ,丁寧に議論をしていきたいと思います.改めまして,発表の機会を与えてくださった世話人の方々,コメントをくださった皆様方,ありがとうございました.
第二部 特別企画 Charles Goodwin 先生追悼特別企画 「協働としてのインタラクション:言語・身体・参与」
「C.Goodwin教授とアジア言語の会話分析」
- 遠藤智子氏(成蹊大学)
不勉強を晒すので非常に恥ずかしい(から報告の際は黙っていた)のだが、実は私は渡米するまでGoodwin論文を一本も読んだことがなかった。2004年の9月、指導教官の陶先生と話した際にChuck Goodwinの授業に是非出るようにと強く薦められたのがその名前を聞いた最初である。このため私にとってGoodwinはCharlesである前にChuckであり、その研究内容を知ったのはあのとんでもない早口で息をつく間もなく展開するトークによってであった。だから今、論文や本という形でしか彼の研究に触れられないことが、なんだかとても不思議な気がする。
今はもう存在しないUCLAの応用言語学科には談話分析を学ぶアジア系学生が多く、また私のように隣のアジア言語文化学科から授業を取りにくる学生もいたため、Goodwin教授のDiscourse Labには日本語・中国語・韓国語等のアジア言語を専門とする大学院生が多数出席していた。Y.Park (2009, Discourse Studies 11(1))、M.Kim (2014, Discourse Processes 51(3), 2016, Text and Talk 35(6))およびLi and Ono編 Multimodality in Chinese Interaction (2018, Mouton de Gruyter)等にGoodwin教授の影響を受けた韓国語・中国語の分析がみられる。
日本語の文法とその相互行為におけるマルチモーダルな形での実現について、Goodwin教授は特に強い興味を抱いていたように思う。Co-operative Actionの第3章第4節では林誠先生の後置詞で始まるターンの分析や岩崎志真子さんのターンの協働的構築に関する分析が詳しく紹介されている。言語学的に考えると後置詞は名詞に付加されるものであり、単独で生起することはありえない。しかし、Hayashi (2001, Studies in Interactional Linguistics, John Benjamins所収) やIwasaki (2012, Embodied Interaction, Cambridge UP所収) が論じた通り、参与者たちはその場で展開しつつある(“unfolding”という言葉をChuckはよく使う)ターンの瞬間瞬間の状態に敏感であり、例えば名詞部分を産出した時点で相手の理解やスタンスを確認し、問題がないとわかってはじめて後置詞を産出してさらなる要素へとつないだりする。文法が命題内容をコードするだけのものではなく、目の前の相手にどう話すかを調整するものでもあることを、これらの研究は大きな説得力をもって示している。
身体を持つ人間同士が顔を合わせて話すとき、どんなに些細なふるまいも意味を持ちうる。そして、相互行為における意味とは片方からもう片方へと一方的に伝達されるものではなく、参与者たちが協働で作りだすものである。このことをGoodwin教授は様々な事例を通じて論じただけでなく、周囲の学生や研究者との議論の中でまさに身をもって実践していた。ChuckのDiscourse Labはもうないけれど、私たちがこれから相互行為を分析するとき、データを見て気づきを語るその言葉の中には彼の言っていたことやものの見方が否応なく含まれるのだから、悲しむべきことなど特に何もないのだろう。
「EMCAの枠組みを超えて――チャールズ・グットウィンによる人間行為探求の飽くなき追求」
- 黒嶋智美氏(玉川大学)
この度は,Chuck先生への追悼企画でお話させていただく機会をいただき,誠にありがとうございました.このお話をいただいて,すぐに先生の論文を改めて読み通す作業に取り組みました.なかでも,先生の最後の出版物となった,Co-operative Actionは,先生がまさに研究人生の最後まで,人間行為がいかに自明的でありながら,複雑なプロセスを経る,他者との協働によって達成されるものであるのか考え続け,論証され続けたその功績が,非常に端的にまとまって示されているマスターピースであると思います.またシンポジウムでも話題になりましたが,先生の多くの研究は,事例分析が深い洞察に裏打ちされた記述によれば可能であることを証明するお手本のような側面もあるといえます.ぜひChuckの論文をそのような観点から読み返してみてください.そのような作業を通して自身の研究への新たな気づきがあることが,Chuckの遺志を受け継ぐことになるのだろうと今は考えています.
「相互行為の鮮やかさを描き出す――身振りの重ね合わせを例に」
- 城綾実氏(滋賀県立大学博士研究員)
本報告では、Charles Goodwin先生の卓越した観察眼、およびそれにより明らかにされてきた相互行為の構造の示し方を「鮮やか」と呼ばせていただき、その仕事の一部を振り返りました。本報告の目標は、Goodwin先生の偉業から学び、そしてEMCA業界に貢献していくにはどうすればいいのかについて、現時点での私なりの思いをお伝えすることでした。それは、目の前の相互行為を、Goodwin先生が残された理論や概念ありきで分析し、彼の理論や概念をより汎用的で強固なものにしていくこととはおそらく違うのではないかと、フロアに、そして誰よりも自分自身に問いかけることでもありました。確かに、“Co-operative Action”の考え方を利用すれば、二人以上で同じ身振りを同時に合わせる現象が組織化されているさまを鮮やかに説明することができるかもしれません。しかしそれは、自分の分析的目的に適ったやり方なのだろうか、と。
Goodwin先生の発表および著作に接していると、とりわけChilにフォーカスした文章から彼の熱意をひしひしと感じます。Chilはただ3語のみを操る者ではなく、それに加えて自他が産出する行為や振る舞い、その場の環境などを利用して豊かで複雑な行為をつくりだすという鮮やかな相互行為能力の持ち主であること。この事実を人びとと共有したいという気持ちが、Goodwin先生のなかでとても強かったのではないかと推察します。Chilが示す行為の産出方法は、どのような人でも何気なく用いている方法であり、さらにはコミュニティとして行為や知をうみだしている方法でもある。このことを緻密で鮮やかな記述により示しているのが“Co-operative Action”であると思います。
Charles Goodwin先生は、彼自身の思いや目的に適ったやり方で数多くの仕事を残されました。では、自分の思いや目的は何か。相互行為が組織されるその巧妙さを人びとと共有したいという素朴な思いだけはありますが、私はまだ発展途上の身であります。西阪仰先生が先日出版された『会話分析の方法――行為と連鎖の組織』のあとがきにて、「既存の概念を精確に使えなければ、自分の新しい概念を精確に使うことは、もっと難しい(ibid: 210)」と述べられていますが、Goodwin先生が残された理論や概念を精確に使える段階にも、私は届いていないように感じます。なので今は、自分の思いや目的を育てながら先行研究に学び、適切な相互行為の記述を目指していきたい、と思っています。
「犬の散歩と相互行為的環世界」
- 細馬宏通氏(滋賀県立大学)
2004年10月から2005年3月までの半年間、UCLAに在外研修で滞在した。その間、Charles Goodwinの研究室に通ったことは思い出深い。11月のある日、チャックは朝5:30にわたしのステイしているアパートに迎えに来てくれて、キャンディや近所の人たちとともに「犬の散歩」へと案内してくれた。なぜそんなありふれたことに誘ってくれたのか、その理由はすぐにわかった。LA郊外の乾燥した丘陵は、草がまばらで、犬たちが道なき道へと人を引っ張っていく。「犬の散歩」とは、犬が世界の中で人を導いていくプロセスであり、犬と人との世界の重なりを体験する時間だった。
ユクスキュルは、各生物は、物理的環境 Umgebung の中でそれぞれ異なる知覚標識から構成される異なる「環世界 Umwelt」を持っている、とした。さらに、ひとつの生物の中でも、状況によって環世界から引き出される「知覚像」は異なるトーンを帯び、特定の「作用像」をもつ行動を引き起こす。環世界・知覚像・作用像の概念は、個体としての生物の世界を表すのに適しているが、そのままでは複数の個体の関わる相互行為の考え方を欠いている。相互行為を記述するには、異なる環世界・知覚像・作用像をもつ複数の個体による相互作用を記述しなくてはならない。本発表では「環世界間の相互作用」問題を、グッドウィンと体験した「犬の散歩」から得た着想を足がかりに、「分解/再利用」「累積 accumulation」の考え方を用いて相互行為の問題へと拡張することを試みる。
ヒトは、複数の環世界・知覚像・作用像を持つものどうしの間で、ごく短時間の間に特定のゴールを達成することができる。そのためには、環世界に埋め込まれている幾多の行為の可能性の中から、特定の行動からなる特定の行為を絞り込む必要がある。こうした絞り込みはいかにして行われるのか。そのヒントは、ヒトは環世界の中に他者を発見するとき、他者を環世界の中でもひときわ特別扱いする動物である点に潜んでいる。ヒトは、他者が環世界に埋め込まれているアフォーダンスを明らかにしてくれると信じている(空間的絞り込み)。ヒトは、相互行為 (もしくはwe-mode) の中で他者がコンマ秒単位の時間の中で自分と微調整を交わしてくれると信じている(時間的絞り込み)。これらの信頼のもとで、ヒトは先行する他者の行為を分解し組み合わせることで自他の行動を予測し、知覚像/作用像を構築する。信頼が持続するあいだ、知覚像/作用像は予測と現実の差異に応じて更新され、その過程が累積し、相互行為が達成される。このような相互行為の時空間のあり方は、最近の認知科学で指摘されている「we-mode」とも親和性がある。一方で、相互行為分析は、行為の要素を分解するだけでなく、その連鎖構造と累積過程に注目する点で、「we-mode」研究と異なっている。
「チャールズ・グッドウィンと法―「プロフェッショナル・ヴィジョン」の法社会学」
- 北村隆憲氏(東海大学)
グッドウィンの「プロフェッショナル・ヴィジョン」論文は,専門職の成員が,コーディング,ハイライティング,グラフィック表象という3つの言説実践による特有の「見方/ヴィジョン」を通じてその専門職固有の現実を創出・維持するとともに,そうした見方の適切な実践を通じて,そのコミュニティの有能なメンバーとして確立されることを,考古学における実践教育場面と,法廷における弁護人による尋問と専門家証人の証言のやり取りという,かなり異質な2つの場面を挙げながら,例証するものである.
報告では,この分析と対照させて,ロドニー・キング事件・裁判への異なる可能な理解として,4つの「ヴィジョン」を提示した.まず,人々の知覚が人種差別的なエピステーメによってあらかじめ規定されていたとする「レイシャル・ヴィジョン」,また,専門家証人が「専門家」としてそもそも認められるか否かは裁判官の裁量に依拠したものであるからグッドウィンの分析は限定的なものであるとする「裁判官ヴィジョン」,また,殴打ビデオは最初の13秒間(キングの突撃シーン)がテレビ局によってカットされており,グッドウィンの分析しなかった(できなかった)ビデオ部分こそが陪審団が警察官の無罪の決定的根拠であったことを明らかにする「メディア・ヴィジョン」,そして,グッドウィンの分析が依拠した「理論負荷性」(ハンソン)の概念がヴィトゲンシュタインの「seeing-as」を誤読するものであるとともに,この分析が,考古学の実地学習場面と問題の多い専門家証人による警察活動の「ミクロ分析」を併置することによって,後者を正当化する見方を可能としている,とするリンチの「ポピュラー・ヴィジョン」を紹介した.リンチによれば,「専門性」が凌駕するこの(法)世界において, “prima facie”のもつ2つの意味のうち,「一見すると(at first sight)」ではなく,「単純明白な(plain and clear)」という意味において映像を理解することが必要であり,その点において,「洗練された(形式)分析」が見失ってしまう現象を当たり前の明白さにおいて日常活動のなかに探求してきたエスノメソドロジーと会話分析とに希望があるという.
報告後,本論文における2つの異質な事例の「並置」についての質問を頂いた.通常,分析上複数の事例を提示することは,事例間の共通性と異質性とを示すことで分析の豊かさをより高めようとするものだろう.本論文では,この「並置」によって全く異質な2事例の間に3つの言説実践を通じた「専門性」の構成という驚くべき同一性・類似性が示されていた.他方で,両事案の決定的な異質性については語られていない.グッドウィンは最後の著書『協働的行為』の第24章として本論文を所収して,前書きのなかでこの分析を「知識と経験の組織化実践の政治的側面」を扱ったもの,とだけ注記している.しかし,キング事件の専門家証人による「プロフェッショナル・ヴィジョン」が,「政治的」意味を持つものであるというグッドウィン自身のこの主張は,彼の分析自体の中でそれとして例証されることはなかった.法のEMCA研究が,「法」のもつまさにその「政治性(権威性/権力性?)」をも経験的に分析しなければならないとすれば,本論文において,「無垢な」考古学事例と弁護人の戦略的言説の分析とが「皮肉なく」併置されるとき,グッドウィンの「美しく精緻な」分析が,まさにそれゆえに引き受けてしまう「危険」にも配視すべきだろう.
以上のように,本報告では,ロドニー・キング事件についての多様な理解の仕方のなかにグッドウィンの「プロフェッショナル・ヴィジョン」分析を位置づけて,それをいったん相対化することを通じて,その分析のもつ強さと弱さの両方について考察し,このことによって,(個人的には),グッドウィンによる本論文を「法のEMCA分析」研究への一つの道標とするための検討を深めようと試みた.

